張機(張仲景)

張機(張仲景)は傷寒雑病論の著者であり、三国時代を代表する医者の一人であり、
医聖とまで呼ばれた人物になります。
ちなみに張仲景は姓+字であり、本来であれば張機の姓+諱の方が一般的ですが、
張仲景の方としての呼び名の方が浸透している事もあり、ここでも張仲景に名前を統一します。
張仲景は、華佗・董奉と共に建安の三名医と言われます。
また張仲景は貧富の差に関係なく、誰であっても公平に治療を施していたといいます。
ある時に華佗が張仲景の著した傷寒雑病論を目にする機会があり、
これを見た華佗は大変に驚きます。
華佗が何に対して驚いたのかというと、
この本には一つ一つの症状についての記録やその治療法が詳しく書かれてあったからです。
建安十三年(208年)に、華佗は曹操によって処刑される事となりますが、
基本的に自らの技術を誰でも彼でもに伝える事を好んでいなかったとされています。
華佗は麻沸散という麻酔を作り出した人物としても知られており、
もしも華佗の医術が後世に伝えられていれば、今の医術はもっと高みに上っていた可能性もあるでしょう。
そういった意味でも病状や対処法をきちんと記録として残した張仲景は、
華佗以上に後世に多大なものを残した人物であると言えるでしょう。
張機(張仲景)発案の餃子

張仲景が餃子を作ったきっかけを辿ると、傷寒雑病論に繋がります。
ある時に張仲景が故郷に戻ると、多くの一族や民衆が寒さと飢えに苦しんでいました。
またそれだけにとどまらず、耳が凍傷になってしまう人が後を絶ちませんでした。
張仲景はこの悲惨な状況を目のあたりした事で、民衆の為になる医者を目指します。
そこで完成したのが傷寒雑病論だったのです。
張仲景は耳が凍傷になっている者達をどうにかして救えないかと苦慮し、
そこで考え出されたのが餃子であり、大釜で茹でた餃子を振る舞ったのが始まりだとされています。
張仲景の餃子は、「寒さを無くして、耳を治す為の飲みもの」という意味を込めて、
正確には去寒嬌耳湯という名称で呼ばれていました。
~張機(張仲景)流の餃子の作り方~
|
餃子と共に釜で煮込んだ湯(スープ)を与えられた者達は、次第と体が温まり血色がよくなっていきます。
そして餃子とスープを毎日飲み続けた人々は、耳の凍傷も完治したといいます。
現在に伝わる餃子
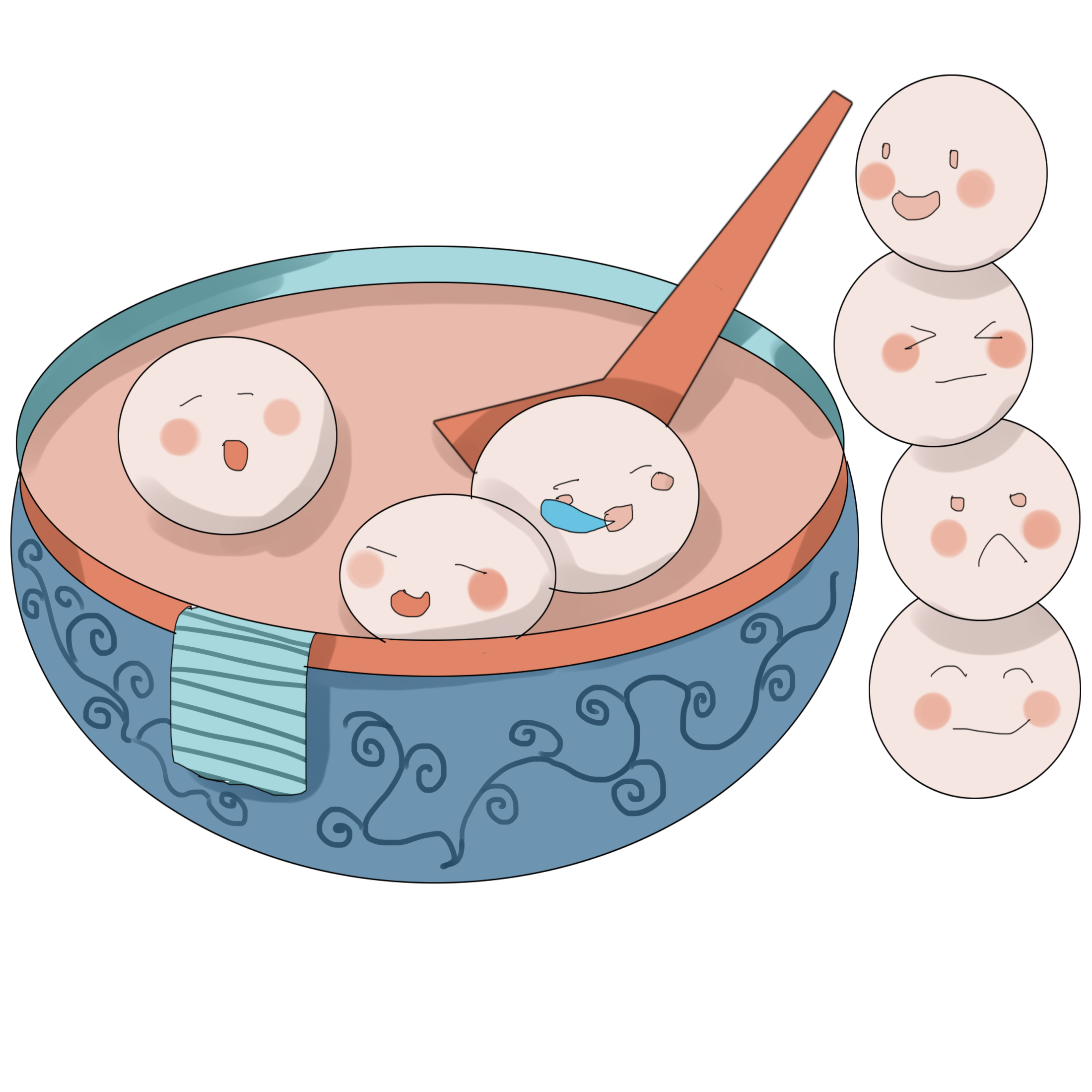
張仲景は正月の前日である大晦日まで、毎日欠かさずに餃子とスープを配り続けたようです。
その餃子が民衆によって広く愛され、張仲景の死後も作られ続ける事となりました。
そして今でも中国では冬至から大晦日の間に餃子を食べるわけですが、
これは餃子を振る舞ってくれた張仲景への敬意を込めての習慣だそうです。
日本で餃子と言えば焼餃子が一般的ですが、中国の餃子と言えば水餃子が一般的です。
それはおそらく最初に張仲景が振る舞ったのが水餃子だったからでしょう。
現在において様々な料理方法(焼き餃子・水餃子・揚げ餃子・蒸し餃子)によって楽しまれている餃子ですが、
その始まりは耳が凍傷となって苦しんでいる人達を救ってあげたいという張仲景の想いから誕生した料理だったのです。
ちなみに日本の正月にお馴染みの屠蘇(酒)は華佗が発案であったり、
デザートとして楽しまれている杏仁豆腐は、董奉という医者によって生み出されているのは余談です。
華佗は言わずもがなですが、董奉もまた後漢末期から三国時代にかけての医者になります。

-100x100.png)



」を現在に伝えた王叔和-1-100x100.png)
