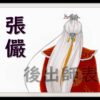樊建(はんけん)

樊建は荊州義陽郡の出身であり、劉禅に仕えた人物になります。
251年に樊建は呉への使者として派遣されるのですが、
その時の孫権はたまたま病に伏しており、諸葛恪が代わりに面会しています。
面会の後に孫権は樊建がどのような人物であったかを尋ねると、
かつて使者として訪れたことがある宗預と比較して
「才能は宗預に及びませんでしたが、性質は宗預以上でありました。」
というのが諸葛恪の樊建に対する評価でした。
後に樊建は侍中に任じられ、董厥に代わって尚書令を務めるまでに出世していきます。
宗預と孫権の逸話

孫権が蜀の使者として大変に高く評価した人物に、
伊籍・鄧芝・費禕・宗預の四人がいます。
ここでは諸葛恪が樊建と比較した宗預の逸話を紹介しておきたいと思います。
234年に諸葛亮が五丈原で亡くなると、
蜀で大きく心配されたのが、呉蜀の関係が崩れ去るのではないかということでした。
まさに劉備が亡くなった時と同じような状況が生まれたわけです。
実際に孫権はこの時に巴丘の兵士を増やしており、
孫権は「諸葛亮の死に乗じて魏が蜀へと攻め込むのではないか?」と思い、
もしもの際は蜀に援軍として送ることができるし、
蜀が魏に滅ぼされることが避けられなかった際は、蜀の領地を切り取る事も可能だと考えていました。
孫権が巴丘の守備兵が増やした事に対して危機感を覚えた劉禅は、
もしもの際に備えて、永安城(白帝城)の守備兵を増やして対応したのです。
それと同時に宗預を使者として呉に派遣します。
宗預と会った孫権は、
「最近永安の守備兵を増やしていると聞いたが、それはいかなる理由なのか?」と問うと、
「呉が巴丘の守備兵を増やせば、蜀が永安の守備兵を増やすのは当然のことです。
そんな事を互いにわざわざ説明することに何の意味があるのでしょうか!?」と返します。
孫権は正直な返答をした宗預を大変に気に入ったといいます。
それからしばらくして宗預が呉へ赴いた際に、孫権は次のような言葉を発して涙しています。
| 宗預殿には常に呉蜀の間の橋渡しをしてくれた。
これに対して感謝しかない。
しかし宗預殿も私も歳を取って気力も衰えてきている。 今回が宗預殿と会える最後になるだろう。 |
そして孫堅はこれまでの感謝の意味も込めて、
宗預に大珠一斛(十斗)を与えて別れを惜しんだのでした。
蜀漢の滅亡

樊建は諸葛瞻や董厥と並んで国政に携わっていくものの、
宦官であった黄皓の暗躍に対応することができないばかりか、
諸葛瞻や董厥までもが黄皓に靡いてしまい、国内は乱れていくことになります。
ただ樊建自身は最後まで黄皓に靡くことだけはありませんでした。
その後に鐘会や鄧艾が攻め込んでくると、
各地で蜀軍は敗れ、最終的に劉禅が降伏したことで蜀は滅亡してしまいます。
そして樊建も劉禅に従って洛陽へと赴くわけですが、
董厥と共に相国参軍に任じられ、それから間もなくして二人は散騎常侍を兼任したといいます。
劉禅に従った者達で列侯に封じられた者達が「蜀志」後主伝に残されていますが、
その一人に樊建の名が残されています。
| 食邑萬戸、賜絹萬匹、奴婢百人、他物稱是。
子孫為三都尉封侯者五十餘人。 尚書令樊建、侍中張紹、光祿大夫譙周、祕書令郤正、殿中督張通並封列侯。 |
- 樊建(尚書令)
- 張紹(侍中)
- 譙周(光禄大夫)
- 郤正(秘書令)
- 張通(殿中督)
ちなみに蜀漢末期の国政を担った樊建と董厥の二人がいましたが、
董厥は黄皓に靡いた事で蜀漢滅亡の一端を担った点なども含めて、
董厥は列侯に封じられなかったのかもしれません。
そうでなければ樊建と同様に、
董厥も列候に封じられてもおかしくない人物だったと思いますからね。
その後の樊建

給事中に任じられていた樊建は、
司馬炎より諸葛亮の治国について尋ねられた事がありました。
その質問に対して樊建は次のように答えます。
| 諸葛亮殿は自分の悪い点を聞いた際には必ず改め、
過ちを押し通そうとすることは一切ありませんでした。
また賞罰の誠実は神明をも感動させるものでありました。 |
これに対して司馬炎は、
「もし私が諸葛亮殿を補佐役にできていれば、今日の苦労はなかったであろう。」
と諸葛亮に対して賛辞を贈っています。
またこの際に無実の罪で殺害された鄧艾の名誉を回復を嘆願し、
鄧艾の罪は死して後に許されることとなったのです。
何故に樊建が蜀を滅ぼした相手である鄧艾の弁明をしたのかは不明ですが、
鄧艾が蜀攻略後にも略奪を働かず、蜀政権の者達を変えずに用いたりと、
益州の安定に努めていた事実を知っていたからこそ、
反逆者として殺害された鄧艾の名誉を回復させてあげたかったのかもしれませんね。
そして鄧艾の子供達こそ既に処刑されていたものの、
西域に流刑となっていた鄧艾の妻と孫の帰還が許され、
273年には孫の鄧朗が郎中に取り立てられているのは余談です。
ちなみにこの逸話以降の樊建がどうなったのかは今に伝わっていません。

」--100x100.png)
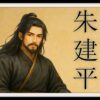
-100x100.png)
の滅亡-100x100.jpg)