二虎競食の計

「二虎競食の計」は荀彧が提案した計略ですが、
どんな計略であるかを説明したいと思います。
この計略は「腹をすかせた二匹の虎に肉を投げ込む」というものです。
そうすると二匹の虎は肉の奪い合いをはじめ、
その争いはどちらかが死ぬまで終わることはなく、
勝利した虎も傷だらけで弱っているだろうから、最低限の労力で二匹とも倒せるというものでした。
一言で言ってしまえば、漁夫の利にも似た計略になりますね。
荀彧の「二虎競食の計」(三国志演義)



横山光輝三国志(10巻11P~13P)
呂布は董卓の殺害に成功したものの、
李傕・郭汜に敗れ、各地を放浪していくわけですが、
そんな呂布が流れ着いた先が徐州を統治していた劉備でもありました。
武勇に優れた呂布が劉備と結びついたことを恐れた曹操は、
なんとか二人が仲違いする方法を模索します。
そこで登場したのが、荀彧の二虎競食の計だったのです。
荀彧の話を聞いた曹操はさっそくこの計略を実行に移します。
まず曹操は献帝から詔勅を頂き、劉備を正式な徐州牧に任じました。
この時の劉備は陶謙から徐州の跡を受け継いではいましたが、非公式の上で継承でした。
今回の徐州牧就任は、徐州の主が劉備であることが、正式に認められたことを意味するわけです。
ただここからが本題で、徐州牧と引き換えに呂布の討伐を命じられることとなります。
しかし曹操のたくらみだと考えた劉備は、呂布を討伐する話をうまくはぐらかしたのです。
これにより二虎競食の計は失敗に終わりました。
ただこれは次の計略である駆虎呑狼の計へと繋がっていくことになります。
何故「二虎競食の計」は失敗したのか!?
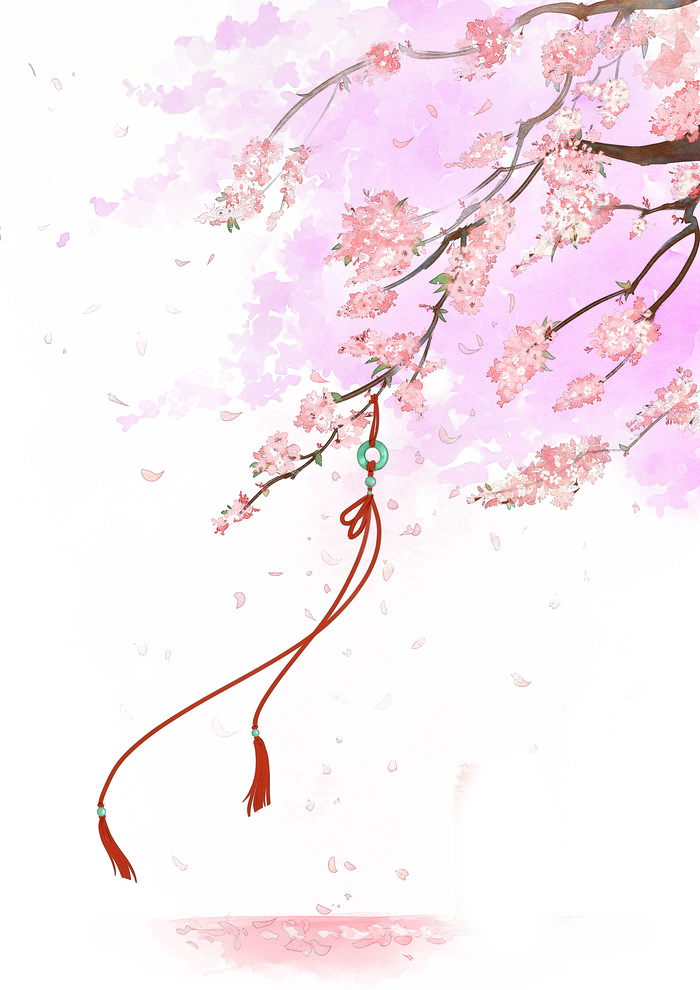
二虎競食の計が失敗に終わってしまったのは、劉備にだけ肉を与えたからでしょう。
二虎競食の計は双方に対して肉、つまり利がなければいけないものですが、
今回は呂布にとって肉にあたるものがありませんでした。
これが失敗に終わった原因だと思われます。
どちらかというと二虎競食の計ではなく、
「一虎誘食」「一虎襲食」みたいな意味合いが強い計略だったかなと個人的には思います。
※実際に一虎誘食・一虎襲食といった計略はありません。
なぜなら上でも述べたように、
劉備を徐州牧で誘惑して呂布を襲わせる意味合いですから・・・
二虎競食の計≒離間の計
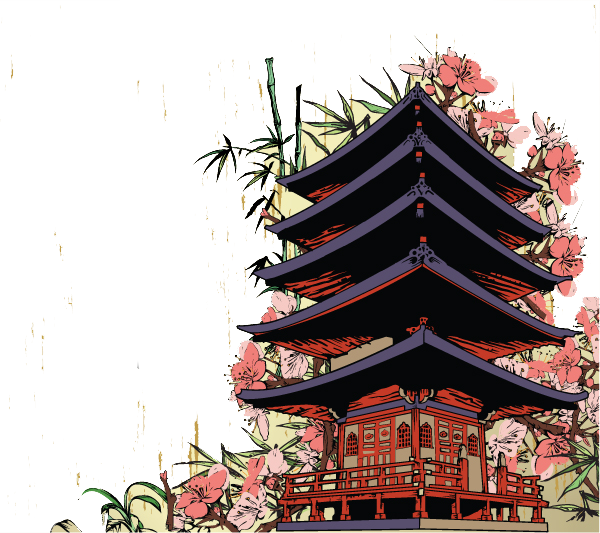
二虎競食の計と大げさな名前こそついてはいましたが、
結局行きつくところの離間の計でしょう。
離間の計は潼関の戦い(211年)で、
賈詡が馬超と韓遂の二人を仲違いさせたことでも知られる計略です。
そして二虎競食の計から繋がる駆虎呑狼の計も、普通に言ってしまえば離間の計です。
他にも王允・貂蝉によって董卓・呂布の関係を悪化させた美女連環の計、
これも結局は離間の計ですからね。
三国志演義は劉備や劉備が建国した蜀漢を主人公にした物語ですから、
劉備に仕掛けられる計略に対して、大層な名前をつけた可能性が高いのだと思います。

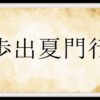

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)


