目次
韓馥から袁紹に乗り換えた審配

審配は当初韓馥に仕えていましたが、
191年に袁紹が自分の領地を獲得すべく韓馥から冀州を奪うと、
そのまま袁紹に仕える事になります。
ちなみにこの時に田豊や沮授も袁紹に轡替えしています。
ちなみに審配と田豊は似たような所があり、
主君であろうとお構いなしに、はっきりしとした物言いだったこともあり、
韓馥から遠ざけられ、重く用いられていなかったという共通点があったりします。
だから二人が韓馥から袁紹に仕えようと思ったのには、それほど時間がかからなかったのだと思います。
ただ新たな主君になった袁紹も、
そういった人物を心のどこかで嫌っている節がありますが、
ただ審配はなんとか袁紹に取り入ります。
一方の田豊はその性格が袁紹に疎まれ、
才能を出し切れずにこの世を去った感じが否めませんが・・・
持久戦VS短期戦
袁紹が曹操を攻めようと考えた際に、田豊・沮授は長期戦を主張した事に対して、
二人に反発するように郭図と審配は短期戦を主張します。
ただ郭図は負け軍師の異名を持つ程に、
毎度のごとく作戦が裏目に出た人物としても後世に知られており、
審配もはっきりと言ってしまえば、郭図と似たようなところがあったりします。
袁紹は田豊・沮授をどこか煙たがってところがあり、郭図・審配の短期戦の意見を採用します。
そしてその戦いは官渡の戦いへと発展し、最終的に鳥巣の食糧庫が焼き払われた事で惨敗を喫したわけです。
短期戦でも勿論勝利した可能性はあったわけですが、
田豊や沮授が主張していた長期戦でじっくりと勝負しておけば、
食糧問題などからも自然と勝利した可能性があっただけに、
勿体なかったかなと思ってしまいますね。
鳥巣の砦が襲われた際の裏話
官渡の決戦で袁紹の敗北が決定してしまうのは、
食糧が貯めこまれていた鳥巣の砦が、曹操軍によって焼き払われてしまった事が原因ですが、
その情報を曹操に仕えた人物がいた事が決め手となります。
その人物とは、曹操と幼き頃の旧友であった許攸という人物ですが、
実は許攸が曹操に寝返った背景には審配の存在があったのです。
これは許攸が曹操へと寝返ることになる少し前の話になりますが、
許攸の家族が法を犯したという理由から捕らえたことがありました。
また許攸は自らの進言が袁紹に聞き入れられなかった事などにも不満を募らせた要因であり、
最終的に曹操へと寝返る事を決意したわけです。
そして鳥巣の弱点を知った曹操は、袁紹との戦いに勝利する事ができたのでした。
この許攸の情報がなければ、曹操が袁紹に負けていた世界線もあったかもしれません。
実際に袁紹との戦いで劣勢を強いられた上に、食糧までも乏しくなり、
さすがの曹操も一旦許昌まで撤退しようかと悩んだ話が「魏志」荀彧伝に残されています。
この際に曹操は荀彧から励まされた事で踏ん張り、
許攸の裏切りへのチャンスを引き込んで勝利を収める事ができたのです。
審配の失脚&復職
袁紹は官渡にて敗北を喫するわけですが、
この時に審配の二人の子供が敵軍に捕まってしまいます。
郭図・辛評は審配が子供の命を救うために曹操に寝返るのではないかと訴え、
それを信じた袁紹により審配は失脚します。
ここで審配を懸命に弁護して救い出したのが逢紀であり、
そのお陰で審配は復職に成功します。
ただ上記のような逸話からは想像ができないかもしれませんが、
それまでの審配と逢紀の関係はあまりよくなかったのです。
しかしこれを機に二人は親密な関係になったといい、
建安七年(202年)5月に袁紹が亡くなった後には二人して袁尚(三男)を支持しています。
袁家分裂の一端を担ぐ

建安七年(202年)5月に袁紹が病没すると、
後継者を決めていなかったことが災いして分裂していきます。
- 袁譚(長男)派←郭図・辛評が支持
- 袁尚(三男)派←審配・逢紀が支持
ただ多くの者達は長男であった袁譚を後継者として推したことが、
「後漢書」袁紹伝に残されています。
しかしここで暗躍したのが審配であり、
袁紹の遺言を偽造して袁尚を後継者に推したと書かれてあります。
その結果、袁譚派と袁尚派に大きく分裂し、国が傾いていくこととなるわけです。
そしてこの跡目争いを好機とばかりに付け込んできたのが曹操であり、
これにより袁家は滅亡の一途を辿っていくこととなります。
鄴城防衛戦

袁譚と袁尚の争いが激化していく中で劣勢を強いられたのが袁譚でした。
そこで袁譚は敵であるはずの曹操に降る形を取ります。
袁尚が袁譚を平原城に追い詰めていた際に、
曹操は手薄となっていた袁尚の居城でもある鄴へと迫ります。
この時に鄴の守りを任されていたのが審配でした。
そして審配は見事なまでに曹操の攻撃を凌いでいくこととなります
| ①蘇由の裏切り
→蘇由の計画を事前に察知して蘇由を討伐に成功。 →蘇由は逃亡して曹操に降伏。
②曹操は地下道を掘って城へ侵入を試みる →城内から塹壕を掘って対応して撃退に成功。
③馮礼が曹操に寝返り、曹操軍を城内に引き入れる →馮礼の裏切りを利用し、 侵入した曹操軍に対して城壁より石を落として壊滅させる。
④曹操による鄴城を水攻め&糧道の確保 →これにより多くが飢え死にするものの、 それでも2カ月以上にわかって鄴城を死守することに成功。 |
審配が孤軍奮闘に何カ月も鄴城を死守していたわけですが、
ここにきて袁尚が平原攻略を諦めて鄴へと戻ることを決断します。
そんな袁尚ですが、曹操に撃破されてしまいます。
そんな中にあっても、審配の防衛戦は続くわけですが、
曹操が鄴城の弱点を探すべく鄴城周辺の偵察をしていた際に、
審配は弩兵により曹操を襲撃したこともあったといいます。
この時の曹操は、運よく逃げられるほどに危なかったとも言われていますね。
審栄(審配の甥)の裏切り&審配の最期
鄴城防衛戦にあたって、蘇由・馮礼の裏切りをはじめ、
地下道攻め・水攻め・食糧攻めと曹操軍の計略を防ぎ続けた審配でしたが、
最後は審栄(審配の甥)が裏切った事で、最後はあっさり勝負は決します。
審栄が城門を開いて曹操軍を招き入れた事で、
審配は激しく市街戦を繰り広げるものの、どうする事もできず審配は捕らえられます。
そして曹操に捕らえられた審配でしたが、曹操を前にしても審配の気力は充実したままで、
審配の大きな声で言葉を発し、それは曹操を威圧するような話し方だったといいます。
そして最後まで弱音を吐く事もなかったと・・・
この審配の様子を見たものは全て感嘆したことが、
「魏志」袁紹伝に残されています。
また「魏志」袁紹伝の裴松之注「先賢行状」には次のような逸話が残されています。
| 曹操「私が先日包囲した際に、何故あれほどまでに弩を射かけてきたのか?」
審配「弩の数が少なすぎたのが残念である。」 |
そんな忠義心に厚く、堂々とした態度の審配を曹操は臣下にしたいと考えるようになるも、
審配は最後まで袁尚への忠義を貫いたのでした。
審配は死刑執行人に怒鳴りつけて、北の方角を向かせると、
「我が君は北におわすのだ」と叫んで首を討たれたといいます。
審配の評価

審配の処刑が済んだ後に、鄴城にある将兵の家を調べてみたところ、
審配の家には莫大の財がため込まれていたといいます。
もしも鄴城で曹操に激しく抵抗した名将ぶりと、
最後まで袁尚に忠義を尽くした審配の姿がなかったならば、
郭図・逢紀同様の評価でしかなかったでしょうね。
ただ鄴城防衛戦・忠義の最期、これが審配の評価を大幅に上げたのは間違いないでしょう。
だからこそ三国志演義においても、
袁家に忠誠を尽くした人物として描かれになったのだと思います。
そんな審配を正史三国志に多くの注釈を加えた裴松之は、
「審配は一代の烈士であり、袁家の真の忠臣でもあり、死を恐れない人物であった。」
と非常に高い評価を与えています。



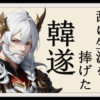
-孫晧死亡のデマに踊らされた佞臣--100x100.png)
-孫晧死亡のデマに踊らされた佞臣--100x100.png)
