劉璋・劉備に仕えた王連(文儀)

王連は荊州南陽郡の人物であり、息子に王山がいたことが分かっています。
そんな王連ですが、どういう経緯で益州に来たのかは不明ですが、
劉焉亡き後の劉璋に仕官し、梓潼の県令に任じられます。
その後に劉璋と劉備との間で戦いが勃発すると、
劉備は葭萌関を霍峻に任せ、自らは成都へ向って侵攻を開始していくわけですが、
劉備が梓潼県に到達した際にも、
王連は城門を閉ざし、最後まで劉備に降伏する事はありませんでした。
劉備は無理に王連が閉ざした城を攻めることはなく、そのまま成都へ向けて軍を進め、
最終的に劉璋が劉備の軍門に降ると、王連も劉備に仕える事となります。
劉備に仕えた王連は、什邡県の県令に任じられ、
その後に広郡県の県令を歴任するわけですが、双方で見事な業績を上げることに成功したといいます。
劉備の益州統治&三つの政策
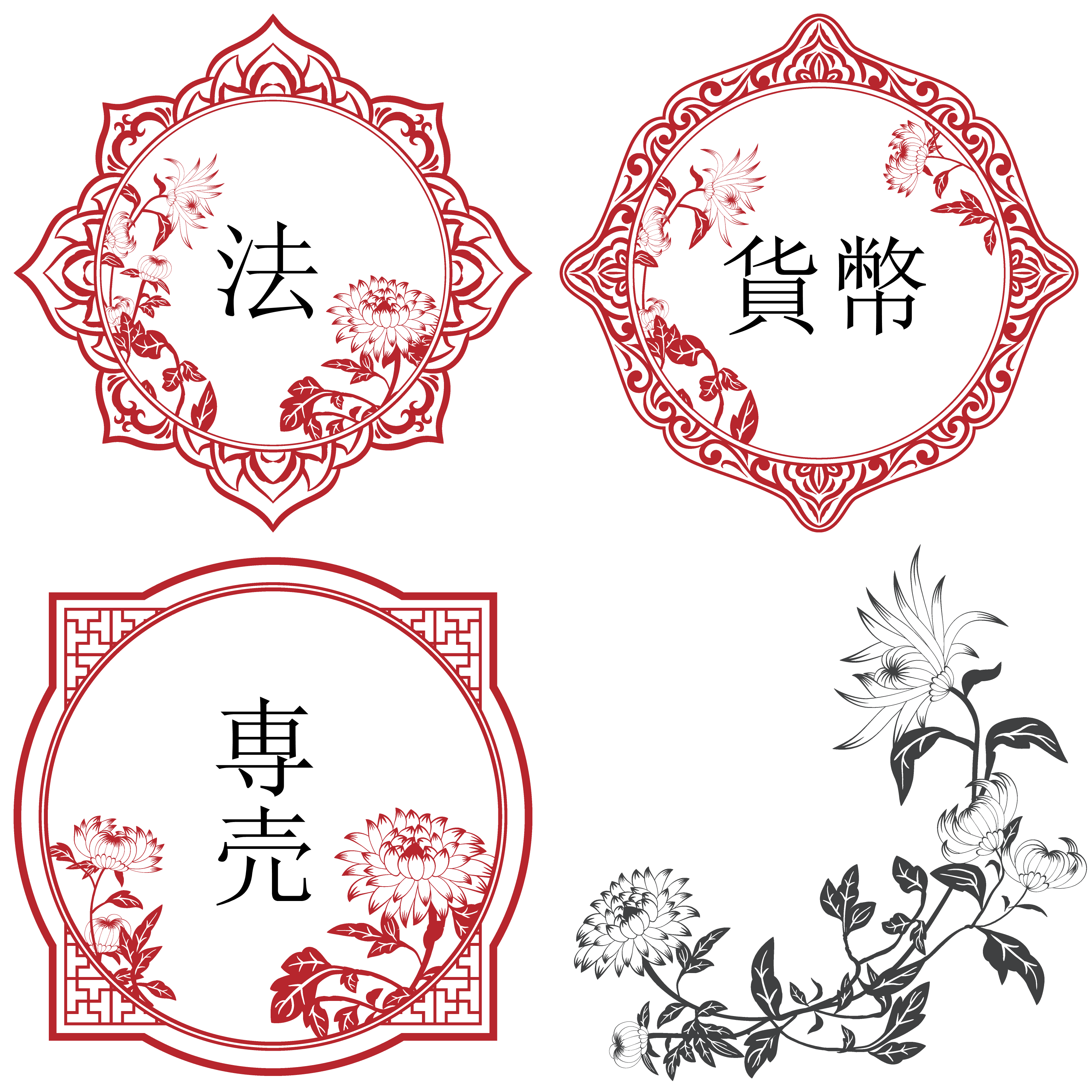
劉備は益州攻略後に取り掛かった事として、大きく三つが挙げられます。
まず一つ目は「蜀科」という益州の法律を作らせたことです。
これは諸葛亮・法正・伊籍・劉巴・李厳らが協力して作り上げており、
を基にしながら国の運営に取り掛かったのでした。
そして二つ目は、劉巴によって貨幣制度が整えられた事であり、
「蜀の貨幣は三国の中で最も優れた貨幣」と後に言われるまでになります。
| 「蜀志」劉巴伝(零陵先賢伝)には、次のように書かれてあります。
劉備は劉璋と激突するより前に、 「私は成都の宝物等は一切に手を付けないから、 お前達が自由に受け取ったり使ってよいぞ。」と部下や兵士達と約束していました。
そして成都攻略後に、劉備はその約束を守り、 将兵達は競って国庫の宝物等を奪い合ったといいます。
これにより劉備は財政難に陥ってしまったわけです。
ここで登場したのが劉璋降伏後に劉備に仕えた劉巴でした。
ただ劉巴は劉備があまり好きではなかったようで、 荊州→交州→益州と劉備の支配から逃れるように逃れてきた人物でもあります。
ただ劉備に仕えてからの劉巴は、 驚くほどの功績も上げたのもまた事実であったりするわけです。
その最大とも言えるのが貨幣制度でしょう。
劉巴は悩む劉備に対して、 「新貨幣を作って物価を安定させ、 役人に市場を任せれば、国庫はすぐにでも溢れるでしょう。」 と助言し、実際に劉巴が言った通りになり、財政が安定していったのでした。 |
そして三つ目に上げられるのが、
国庫に大きな利益をもたらした塩府校尉の設置でしょう。
塩府校尉の役割は、益州の豊富な鉱物資源である鉄であったり、
これまた益州各地に存在していた塩により財政を更に豊かにしようとしたものでした。
この大事な役割を任されたのが、
什邡県・広郡県で見事な結果を残していた王連だったのです。
そして王連は劉備の期待に見事応え、国に大きな利益をもたらしたのでした。
また王連はこの時に塩府校尉の補佐的役割を担う属官として、
呂乂・杜祺・劉幹を典曹校尉として採用しています。
呂乂は後に巴西・漢中・広漢・蜀郡の太守を歴任した人物でもあり、
董允亡き後は尚書令として活躍するなど、蜀漢を大きく担う人物として活躍していますし、
杜祺は監軍・大将軍司馬にまで出世したり、
二人に及ばないまでも劉幹も巴西太守に任じられています。
この事からも王連の人を見る目も確かだったことがうかがえる逸話になるでしょうね。
ちなみにですが廖立は劉備や関羽を筆頭に、
多くの者達を批判した事で官職を剝がされて庶民に落とされた人物ですが、
廖立は王連を次のように評価していました。
| 「王連流俗、苟作苛斂、使百姓疲弊以致今日。」 |
ここには「王連のようなくだらない人物が、
偉そうな顔で民衆を疲弊させたから、今日の事態を招いたのだ。」
と廖立が王連を非難した内容が描かれている感じです。
ちなみに廖立が非難した人物に、
王連以外に劉備・関羽・向朗・郭攸之・文恭らの名前が挙がっていますが、
彼らの生涯を見る限り、あながち間違った事を言っていなかったようにも思います。
この事から考えられることとしては、
王連は塩・鉄の専売によって大きな利益をもたらしたのかもしれませんが、
その為にその地に住む民衆であったり、
異民族に大きな負担をかけていたのではないでしょうかね。
例えば塩や鉄により既に利益を得ていた者達がいたとすれば、
その収入源を奪われた事により反乱なども当たり前にあったような気がします。
その結果として廖立は、
「王連の政策のせいで、反乱が勃発するまでの事態になってしまっている。」
と言いたかったのかもしれませんね。
その後の王連

王連は塩府校尉を兼務する形で、
新たに蜀郡太守・興業将軍に任じられています。
これの意味する所として、王連のもたらす塩や鉄の国益が非常に大きかったのでしょう。
だからこそ王連に引き継がせたのだと思いますね。
建興元年(223年)に入ると、
屯騎校尉・丞相長史に任じられ、諸葛亮を近くで支えています。
またこの時に平陽亭侯にも封じられています。
ちなみに宿営兵を統率する役割のある屯騎校尉は、孟光・宗預も任じられた官職であり、
丞相長史は、向朗や楊儀が任じられた事でも知られる官職です。
そして益州南部で雍闓が反乱を起こすと、
それに呼応する形で高定・朱褒らが反旗を翻したわけですが、
この時に諸葛亮は自ら反乱討伐に向かおうとします。
しかし王連は、風土病など危険性から、
これから国を立て直す中心的人物である諸葛亮自らが、
僻地の討伐に向かう事に大きく反対しています。
劉備亡き後の大事な時期であったからこそ、王連の意見は最もな意見だったと私は思いますね。
また諸葛亮は王連の意見を聞き入れ、討伐は延期していたといいます。
ただ諸葛亮は、その間に雍闓と孫権の繋がりを断ち切る為に、
鄧芝を呉に派遣し、蜀呉の関係修復に努めたのでした。
それから間もなくして王連が亡くなると、諸葛亮は反乱討伐に自ら向かっています。
建興三年(225年)の春のことでした。
そしてその年の秋には、諸葛亮は見事に南方討伐を成し遂げています。
その後の諸葛亮は、「漢王朝復興」を目指して北伐へと乗り出していく事となるのでした。
諸葛亮の益州南部討伐の真の目的は!?

雍闓・高定・朱褒らの反乱平定に向かった諸葛亮ですが、
反乱軍の討伐が一番の目的であり、
それに伴う人材確保や兵力確保も目的にあった事と思います。
また雍闓ら反乱軍に抵抗を続けていた人物に王伉・呂凱らがいたのですが、
二人を救いにいく目的もあったことでしょう。
ただそれらはあくまで表向きの理由だと思うわけです。
王連が亡くなった事による鉄・塩からの収入源が落ちる事が推測された中で、
新たな資源獲得を得ようとする考えも大なり小なり、諸葛亮の中にあったことでしょう。
そしてその延長線上として、
西南シルクロードの確保も視野においていたのではないかと私は思います。
敦煌などを通る北方シルクロードよりも歴史が古いと言われている西南シルクロードの確保、
そこからもたらされる莫大な利益も諸葛亮の脳裏にあったと考えるのが自然だと思います。
そして北伐の際には、
北方シルクロードの確保を目指したと思うのが自然なわけです。
南と北のシルクロードの両方を抑える事で、莫大な利益がもたらされることは、
諸葛亮でなくても想像にかたくない事でしょう。
実際に第一次北伐時には、諸葛亮が長安より離れた涼州方面へと兵を進め、
一時は南安・天水・安定の三郡を支配下にすることに成功しているのもまた事実なわけです。

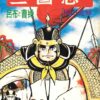

の生涯-1-100x100.png)


