「餃子」といえば、中国の方だけでなく、
日本の人々にとっても当たり前に食べられているものですが、
「餃子が張仲景(張機)によって作られた」という事を知る人は、
あまりいないかもしれませんね。
そんな張仲景と餃子の関係について、ここでは見ていきます。
張仲景(張機)

張仲景と言えば、「傷寒雑難病」の著者であり、
三国時代に活躍した医者の一人であり、
「医聖」とまで呼ばれた人物になります。
ちなみに張仲景以外にも、華佗・董奉を加えて、
「建安の三名医」とよばれたりもします。
張仲景は、患者が金持ちであろうと貧乏であろうと、
差別することなく、平等に治療を行ってあげていたそうです。
ある時、「神医」と呼ばれた華佗は、
張仲景の「傷寒雑難病」を目にしたときに、
一つ一つの症状について記載しているだけでなく、
適切な処方の仕方まで丁寧に書かれていたのを見て驚いたといいます。
おそらく華佗の考えとして、
「そういったものは公表するべきではない!」
という考えがあったからかもしれませんね。
そういった意味では、
「後世の為に適切な治療方法を記録として残した張仲景の方が
華佗よりも色々な意味で優れていた」と言えるかもしれません。
結局のところ、
華佗の医術の知識は伝わっていないのですからね。
張仲景発案の「餃子」

張仲景が餃子を作ったきっかけは、
「傷寒雑難病」について記載したことにつながってきます。
ある時、張仲景が故郷に戻った際に、
一族や民衆の多くが寒さと飢えに苦しんでいる状態で、
耳が凍傷になってしまう人が後を絶ちませんでした。
この頃から、民衆の為に治療できる医者になりたいと張仲景は強く思い、
後に「傷寒雑難病」の本を世に出すわけですが、
この時の張仲景は耳が凍傷になっている者達に対して、
どうにか治してあげられないかと考えた方法として、
「餃子」を考え出します。
そして大きな釜で餃子を作って凍傷にかかった者達に振舞ったのが、
餃子の始まりだと言われています。
この餃子は、正確には「去寒嬌耳湯」という呼び名で、
直訳すると「寒さを無くして、耳を治す為の飲み物」という意味になりますね。
また張仲景による餃子の作り方は以下のような手順でした。
- 羊肉・唐辛子・薬草を釜で一緒に煮込む。
- 煮込み終わった羊肉・唐辛子・薬草を取り出して細かく刻む。
- 小麦粉を薄く広げたものに刻んだ羊肉・唐辛子・薬草を耳の形に包む。
- 包んだものを羊肉・唐辛子・薬草を煮込んだ釜で再度煮る。
餃子と釜で一緒に煮込んだ湯(スープ)を与えられた者達は、
体が温まり、血色がよくなっていきました。
そして餃子とスープを毎日飲み続けた者は、耳の凍傷も完治したそうですよ。
現在に伝わる「餃子」
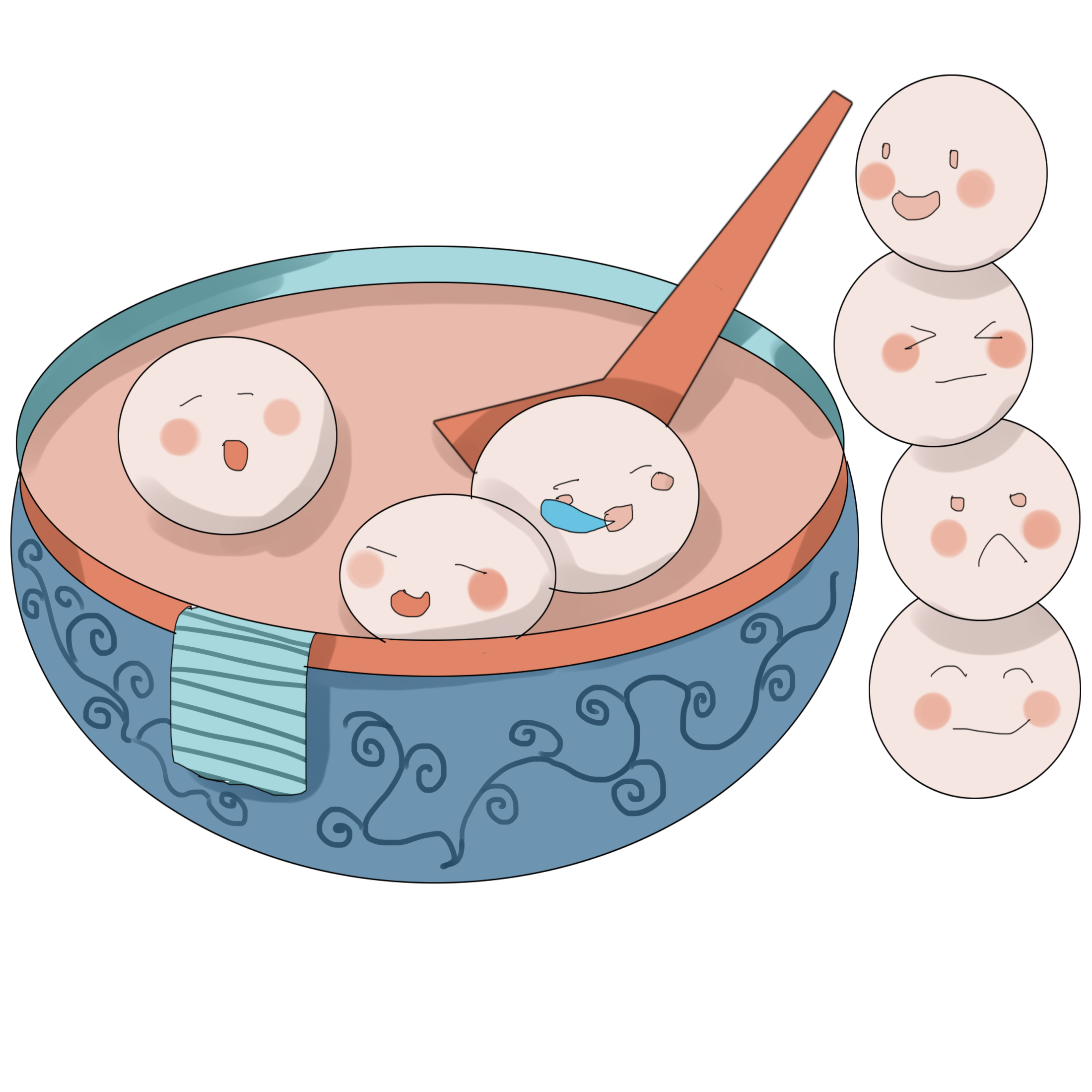
張仲景は正月の前日にあたる大晦日まで、
毎日この餃子とスープを民衆に配り続けたといいます。
張仲景が振舞った餃子は、民衆によって広く愛され、
張仲景が亡くなった後も、餃子は民衆の間で作られ続けていきます。
今でも中国では冬至から大晦日の間に、
張仲景への敬意から餃子を食べるという習慣が残っているそうです。
中国では水餃子が多くの人達に食べられているのは、
張仲景が釜で煮込んで作ったのが始まりだったからでしょう。
今現在、焼き餃子・水餃子・揚げ餃子・蒸し餃子など、
様々な餃子が世界中の人達に食べられていますが、
今から約1800年前に張仲景が考え出して、民衆に振舞っていなかったならば、
餃子という食べ物は今の世の中になかったかもしれませんね。

-100x100.png)


-100x100.png)
」を現在に伝えた王叔和-1-100x100.png)
