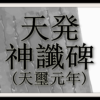陸凱 –陸遜の一族-

陸凱は陸遜の一族にあたる人物になります。
一族と大雑把に言ったのには理由があり、
陸凱の父親だけでなく、祖父や曾祖父が誰だったのかも分かってないからです。
今に伝わっているのは弟に陸胤がおり、息子に陸禕が生まれてるいった記録であり、
陸凱・陸胤兄弟より後の家系図のみが伝えられている形になります。
右肩上がりの出世
陸凱は孫権に仕えて順調に出世していきますが、
建武都尉に任じられた時には兵権を預けられています。
また陸凱が儋耳太守を任された時には賊討伐で活躍し、建武校尉へと昇進しています。
それ以降も魏との戦いや異民族討伐伐で活躍していった陸凱は、
巴丘督・偏将軍に任じられただけでなく、都郷侯にも封じられています。
そして時代が流れ、孫権・孫亮・孫休と時代が流れていくわけですが、
孫休の治世下では征北将軍となり、仮節を与えられ豫州牧を任されています。
ちなみに豫州は当然のように魏領になりますので、形だけの役職になります。
孫休崩御後、孫晧の治世下では鎮西大将軍へと昇進し、
巴丘督・荊州牧にも任命され、嘉興侯の爵位にも封じられています。
晋戦に反対
その後に蜀が魏によって滅ぼされるものの、
その魏も司馬炎が建国した晋によって滅ぼされてしまいます。
魏呉蜀の三国の中で最後まで生き残った呉でしたが、
孫権時代の二宮の変、そして孫晧による悪政により国は大きく傾いていました。
また交州を失うなど、領土的にも劣勢に追いやられていたわけです。
そこで孫晧は司馬炎と盟約を結ぼうと考え、
司馬炎の父親にあたる司馬昭の弔問を口実に、丁忠・張儼らが使者として送られます。
しかし丁忠は孫晧に対して次のように進言します。(張儼は帰国途中に病死)
| 現在、北の備えが手薄でありましたので、不意をついて弋陽を攻めれば奪えるでしょう。 |
この丁忠の提案に劉纂が乗っかった事で、孫晧が弋陽攻撃の命令を出そうとするものの、
陸凱が大反対したことで、弋陽攻撃の命令が出される事はありませんでした。
孫晧廃立計画

266年に左丞相に昇進した陸凱でしたが、
今の現状を大変に憂いて孫晧の廃立計画を練ります。
これに丁奉も賛成したものの、最終的に留平によって反対されたことで断念したといいます。
そんな留平ですが、この5年後に孫晧を見限る発言をしたことで、
留平は孫晧から毒酒を送られており、この時のショックで憤死しています。
国を想っての発言であっても、
孫晧の機嫌を損なうだけで処刑されることが後を絶たない中で、
廃立計画までも立てた陸凱が処罰されなかったのは異例中の異例ですね。
おそらく陸凱が名門であった陸氏であったことがまず第一の理由でしょうし、
陸凱が孫家四代に仕えた重臣であっあことや一族に陸抗がいた事も理由の一つでしょう。
また陸凱同様に孫家四代に仕えた重臣である丁奉も、
孫晧廃立計画に賛同したり、万彧・留平同様に孫晧を見限る発言をしてるにも関わらず、
孫晧から罰せられることはなかったのも驚くべきことではあるわけですが・・・
ただ丁奉の息子である丁温は、丁奉が犯した罪を思い出されたかのように殺害されています。
陸凱の最期

最期まで呉を想って孫晧への忠言を続けた陸凱でしたが、
その言葉の多くが孫晧の心に届くことはないままに病死してしまいます。
ただ陸凱が亡くなる間際に次のような言葉を、孫晧に対して残しています。
| 何定のことは信用せずに地方官に左遷するべきでしょう。
また奚熙もしょうもない人物ですので、彼の言葉も聞いてはなりません。
一方で姚信・楼玄・賀邵 ・張悌・郭逴・薛瑩・滕脩、 そして私の族弟でもある陸喜・陸抗らは才能豊かな者達であり、国を良い方向に導くことができます。
陛下がこの者達の言葉に耳を傾けるならば、 彼らは忠義を尽くし、懸命に陛下を補佐してくれることでしょう。 |
これらの言葉を孫晧に伝えたのが董朝でしたが、
孫晧の恐怖政治を徹底的に批判した上奏文を託したという記録が残されています。
最期まで孫晧から罰せられることのなかった陸凱ですが、
族弟であった陸抗までもが亡くなると、残された陸凱の家族は交州の地へ飛ばしています。
とりあえず既にこの時の交州は晋の領土になっていたと思われますので、
陸凱をよく思っていなかった孫晧が、残された家族を呉から追い出した形だったのかもしれません。
もしくは交州でも少なからず支配地域がまだ残っており、
その地へと送られた可能性も否定できませんが・・・
そんな陸凱ですが、陳寿は次のように評価しています。
| 最期の上奏については、疑う余地はあるけれども、
終始一貫して国の事を、真剣に想い続けた陸凱は立派である。 |
また呉が滅亡した後の288年に、陸抗の四男である陸機は「弁亡論」を著し、
その中で陸凱のことを非常に高く評価していたりもしますね。


-孫晧に最後の最後まで付き従った正妻--100x100.png)
-100x100.png)