「漢(前漢)」王朝の建国

始皇帝により中華統一を成し遂げた秦が劉邦・項羽らによって滅ぼされ、
劉邦が漢楚の戦い(劉邦VS項羽)の勝利を経て、皇帝に即位して開いた王朝を漢(前漢)といいます。
また劉邦の事を高祖と呼ぶことも多いです。
~秦滅亡前の歴史~
|
紀元前202年に誕生した漢王朝ですが、
紀元前が明けた西暦8年までの約210年間続く事となります。
ちなみに秦が滅亡した紀元前206年に、劉邦が漢王に任じられたわけですが、
ここから漢王朝が始まったと解釈する考え方もあります。
ただ一般的には垓下の戦いにて項羽を滅ぼし、
劉邦が皇帝に即位した紀元前202年を漢王朝の誕生年と考える方が自然です。
「新」王朝の建国
初始元年(西暦8年)に、外戚であった王莽の簒奪によって漢(前漢)は滅びます。
※一般的に外戚とは、皇后(皇帝の正妻)の親族のことを言います。
ちなみに形式上は禅譲であり、あくまで譲ってもらったという形が取られており、
後に曹丕が魏を建国した際も、司馬炎が晋を建国した際も禅譲にて譲ってもらったという形を取っています。
そして後の者達は王莽の禅譲を参考にして行ったわけです。
ただ実際には簒奪となんら変わりがないのが実情でもあったのは余談です。
そして王莽が建国した新は、地皇四年(23年)までの約15年の統治が続きますが、
赤眉軍や緑林軍の乱によって弱体化し、最終的に緑林軍に擁立された劉玄(更始帝)によって討ち取られます。
これによって王莽が建国した新は一代で滅亡するわけですが、
そんな劉玄(更始帝)もまた、赤眉軍に擁立された劉盆子に降伏するものの最終的に殺害されています。
〈禅譲→徳が高い人物に、平和的皇位を譲る行為〉
※伝説上の人物である五帝による禅譲の逸話は除いています。
〈放伐→徳が高い人物が武力を用いて、前王朝の暴君や暗君を力で討伐する行為〉
※「湯武放伐」の故事成語はここから誕生しています。
〈簒奪→正当な権利がないにも関わらず、権力や地位を奪う行為〉 |
「漢(後漢)」王朝の建国

王莽への禅譲と王莽の死という時代を経て混乱していた状況下にあったものの、
最終的にこの混乱を治めたのが劉秀(光武帝)でした。
この劉秀という人物ですが、劉邦(初代)から数えて九代目にあたる人物であり、
劉邦(初代)から数えると九代目の末裔にあたります。
また劉秀は建武元年(25年)の際に皇帝に即位しており、王莽によって滅亡した漢(後漢)を再び建国しています。
その後の劉秀は赤眉軍を打ち破り、建武十二年(36年)に中華を再び統一に成功しています。
|
ただ残念なことに国が安定したのは、
劉秀(光武帝)・劉荘(明帝)・劉炟(章帝)の三世代まででした。
その後は劉肇(和帝)の治世下では外戚や宦官の台頭であったり、幼帝が続いたりしたことで国が混乱していったからです。
| 歴代 | 姓諱 | 諡号 | 在位期間 | 年号 |
|---|---|---|---|---|
| 1代目 | 劉秀 | 光武帝 | 23年 ~57年 | 建武25年~56年 建武中元56年~57年 |
| 2代目 | 劉荘 | 明帝 | 57年~75年 | 永平58年~75年 |
| 3代目 | 劉炟 | 章帝 | 75年~88年 | 建初76年~84年 元和84年~87年 章和87年~89年 |
| 4代目 | 劉肇 | 和帝 | 88年~105年 | 永元89年~105年 元興105年 |
| 5代目 | 劉隆 | 殤帝 | 105年~106年 | 延平106年 |
| 6代目 | 劉祜 | 安帝 | 106年~125年 | 永初107年~113年 元初114年~120年 永寧120年~121年 建光121年~122年 延光122年~125年 |
| 7代目 | 劉懿 | 少帝 | 125年 | |
| 8代目 | 劉保 | 順帝 | 125年~144年 | 永建126年~132年 陽嘉132年~135年 永和136年~141年 漢安142年~144年 建康144年 |
| 9代目 | 劉炳 | 沖帝 | 144年~145年 | 永憙145年 |
| 10代目 | 劉纘 | 質帝 | 145年~146年 | 本初146年 |
| 11代目 | 劉志 | 桓帝 | 146年~167年 | 建和147年~149年 和平150年 元嘉151年~152年 永興153年~155年 永寿155年~158年 延熹158年~167年 永康167年 |
| 12代目 | 劉宏 | 霊帝 | 168年~189年 | 建寧168年~172年 熹平172年~178年 光和178年~184年 中平184年~189年 |
| 13代目 | 劉弁 | 少帝 | 189年 | 光熹189年(約5カ月) 昭寧189年(3日のみ) |
| 14代目 | 劉協 | 献帝 | 189年~220年 | 永漢189年(約4カ月) 中平189年 初平190年~193年 興平194年~195年 建安196年~220年 延康 220年 |
劉宏(霊帝)・劉弁(少帝)・劉協(献帝)の治世下の元号が複雑なので解説しておきますが、
中平六年は4月に劉宏が亡くなり、劉弁が即位した際に光熹に改元されています。
その後の宮中の混乱の中で董卓によって劉弁が保護されると、新たに昭寧と改められた流れとなります。
しかし董卓によって劉弁が廃帝とされ、劉協が9月に即位した際に永漢に改められ、
12月に再度劉宏の際の元号であった中元に戻されてます。
ちなみに翌年にあたる190年には、中元から初平に改元されています。
後漢は劉秀から14代目の劉協まで続くわけですが、
即位時に20歳を超えていたものは劉秀(初代)&劉荘(二代目)のみであり、
それに合わせて短命な皇帝が多かったのもまた漢王朝(後漢)が衰退していく原因となっています。
ちなみに5代目の皇帝となった劉隆(殤帝)なんかは、
生後100日程度で皇帝となっており、二歳になったかどうかの年齢で崩御しています。
また9代目となる劉炳(沖帝)も2歳という年齢で即位させられており、
あっさり3歳で崩御するにいたっています。
こういう状態が続いたことで漢王朝の権威は次第に失墜していき、
その中で大きな力を自然と持ってきたのが外戚であり、宦官でもあったわけです。
そんな中で劉宏(霊帝)の時代に張角率いる黄巾の乱が勃発し、
漢王朝の権威は地に落ちてしまいます。
そして董卓による劉弁(少帝)の廃位、劉協(献帝)の即位へと時代は流れていきます。
しかし最終的に曹操の息子である曹丕によって漢は滅ぼされてしまうこととなり、
これをもって漢王朝は終わりを告げる事となります。
ただ後に劉備が益州にて漢を再興させるわけですが、
前漢・後漢と比較する形で一般的に季漢と呼ばれています。
※「季」には末っ子というような意味があり、漢の末っ子という意味で使われています。
ただ三国志演義などの影響もあり、
蜀や蜀漢としての呼び名の方が有名かもしれませんね。

-100x100.jpg)
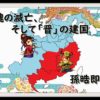
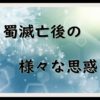
の滅亡-100x100.jpg)

