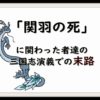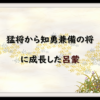呉下の阿蒙(呉下阿蒙)

呉下の阿蒙とは、いつまで経っても成長しない人物を指す言葉です。
阿蒙とは呂蒙の事であり、そんな呂蒙の諱である蒙に「阿」をつけて馬鹿にしたような言葉になります。
一般的に小さい時の幼名として「阿」がつけられる事が多いですね。
例えば曹操(孟徳)の幼名は阿瞞であり、
劉禅の幼名が阿斗であったことはよく知られています。
この逸話を語る上でセットとして語られる故事成語として、
「士別れて三日ならば、即ち更に刮目して相待つべし(士別三日、即更刮目相待。)」が共に挙げられます。
日本では「男子三日会わざれば刮目して見よ」として使われる事も多いです。
意味はどちらも同じですが、人は短い間でも大きく成長できるものなので、
次に会った時には注意して見る必要があるといった意味があります。
単刀直入に言うと、人は短期間でも大きく成長できる生き物だという事ですね。
ちなみにこの二つの故事成語は、「呉志」呂蒙伝の本文でなく、
裴松之が注釈を加えた「江表伝」に記載が残されている内容であり、
呉の孫権に仕えた魯粛&呂蒙のやり取りの中で生まれた故事成語になります。
二つの故事成語が登場する「呉志」呂蒙伝の裴松之注(江表伝) -原文&翻訳-
二つの故事成語の文言が登場する江表伝ですが、
もともと注釈の始まりとしては、武力一辺倒であった呂蒙・蒋欽の二人に対して、
主君でもあった孫権が学ぶことの大事さを説いた事に始まります。
軍務の忙しさから読書をして学ぶ時間はないという呂蒙に対して、
孫権自身が幼い頃より「詩」「書経」「礼記」「左伝」「国語」であったり、
「三史(史記・漢書・東観漢記)」や書家の兵法書などを歴学してきた事を例にとり、
学ぶことで自らの役に立つことも多いであろうことを諭し、
まず「孫子」「六韜」「左伝」「国語」「三史」をすすめて呂蒙を諭した事がきっかけとなり、
呂蒙は多くの書物を読み漁り、文武を備えた人物へと成長していった話が残されています。
以下の原文はその後に続く故事成語に関するものになります。
| 後魯肅上代周瑜、過蒙言議、常欲受屈。
後に魯粛が長江の上流へ遡って周瑜の役目を引き継いだ際に、 呂蒙のもとを訪れて議論を行ったが、常に言い負かされそうになった。
肅拊蒙背曰「吾謂大弟但有武略耳、至於今者、学識英博、非復呉下阿蒙。」 魯粛は呂蒙の背中をトントンと叩きながら、 「私は呂蒙殿が武力一辺倒の人物だと思っていたけれども、 今では学識豊かで、呉の町にいた頃の蒙ちゃん(呉下の阿蒙)とは言えなくなってしまった。」
蒙曰「士別三日、即更刮目相待。」 呂蒙は「優れた者と三日も会わない事があれば、 その相手と次に会う時は注意して見なければいけない。」と言った。
※ちなみに呂蒙の言葉はこの後も続き、荊州を治める関羽への対策の話になっていきます。 |