蒋琬の病死・費禕の暗殺

諸葛亮亡き後の蜀を支えてきた蒋琬でしたが、
長期にわたって体調を崩すこようになっていきます。
蒋琬と言えば魏打倒を考えるというよりも、
蜀の現状維持に努めた程度のイメージを持っている方も多いかもしれませんが、
諸葛亮の遺志を引き継いで、
北伐に積極的に乗り出そうとした人物でもあります。
実際念蜜に計画を考え、
漢水を使う北伐ルートを実行しようとしたこともありました。
諸葛亮が絶対に用いる事がないような侵攻ルートですが、
十分に可能性があったと思いますね。
ただこれは蒋琬の病気が悪化してしまった為に幻の北伐となってしまったんですが・・・
そして蒋琬の病は完全に回復することなく、最終的に没してしまいます。
蒋琬が亡くなると、費禕が蒋琬の後釜につくことになります。
費禕は諸葛亮・蒋琬と違い、積極的に北伐を行う事はせず、
国力増大に力を入れ、優秀な人物が出てくるのを気長に待つことにしました。
北伐を行いたい姜維と何度も意見の対立が起こったようですが、
費禕が姜維を抑えているという構図だったのです。
ただ費禕が戦が苦手だったということはなく、
魏の曹爽が侵攻してきた際は「ちょっと出かけてくる!」といって漢中へと出向き、
王平と協力しながら曹爽の遠征軍をコテンパンにやっつけたりしています。
https://daisuki-sangokushi.com/2020/02/25/%e5%a8%81%e5%8b%a2%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e5%a8%81%e5%8b%a2%e3%82%92%e5%a4%b1%e5%a2%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e6%9b%b9%e7%88%bd/
戦に勝利して戻ってくると、
何事もなかったかのように職務にとりかかったというから、
この逸話だけでも費禕がそうそうたる人物だということが分かります。
ただ現在の蜀の内部情勢を考えた際に、
国力増大に力をいれる事が最優先だと費禕は考えたのだと思います。
そんな国力増大に励んでいた費禕でしたが、
魏の降将であった郭循によって正月の宴会の席で殺害されてしまっています。
これによって北伐を行いたい姜維を止める事ができる者がいなくなり、
姜維が魏打倒に向けて動き出すことになったわけですね。
https://daisuki-sangokushi.com/2021/06/30/%e8%b2%bb%e7%a6%95-%e8%9c%80%e3%82%92%e6%94%af%e3%81%88%e3%81%9f%e6%9c%80%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%9b%9b%e7%9b%b8%e3%80%8d/
姜維の北伐開始

姜維諸葛亮が第一次北伐の際に魏から蜀へ降伏した武将でした。
姜維の類いまれなる才能は諸葛亮によって認められ、
諸葛亮の北伐で作戦上欠かせない一人になっただけでなく、
諸葛亮の兵法を吸収していった人物でもあり、遺言の際は軍事面を託された人物でもありました。
姜維は諸葛亮の遺志を引き継いで北伐をかねてより行いたかったのですが、
蒋琬・費禕の時は抑えられていた事もあり、北伐を決行することができなかったのです。
しかし蒋琬・費禕が亡くなってしまったことで、
姜維を止める者がいなくなり、姜維は北伐を開始します。
姜維は北伐を何度も行い、良い結果を残した時もったのですが、
悪い結果に終わった北伐も多かったのです。
ただ諸葛亮の北伐と大きく異なったのは、
姜維の度重なる北伐によって大きく国力が低下していったことでした。
曹芳廃位による曹髦即位
司馬懿がクーデターを起こしたことで司馬一族の権力が増大していました。
その後に司馬懿はなくなってしまいますが、
息子の司馬師・司馬昭が魏の実権を握るという感じになります。
ただこの時に欠かしてはいけない女性がいます。
郭氏(郭皇太后)といって曹叡の妻なんですけど、
曹叡の養子となっていた曹芳の裏ボス的な存在でもありました。
司馬一族が大きな権力をもっていたのは間違いないですが、
表面上は郭皇太后の承認を得るという流れができていたほどだったといいます。
毌丘倹が反乱を起こした際や蜀を滅ぼして反乱を起こした鍾会などは、
郭皇太后の命での反乱だと言っていたほどでした。
それほど国内で影響力が強い女性だったのです。
ただ司馬師によって曹芳が廃位に追い込まれるのですが、
その時に郭皇太后が大きく反対できなかったのは、
自分が進めた曹芳の妻であった張皇后の父親である張緝が、司馬師追放を試みて失敗したからです。
これに怒りを覚えた司馬師は、
「成人しても酒と女に溺れ、国の政治を全く考えていない!」
といった感じで廃位に追い込んだ感じですね。
ただ郭皇太后は、跡継ぎは司馬師・司馬昭らが薦める人物ではなく、
曹叡の異母兄の曹霖の子にあたる曹髦を強く推薦したのです。
郭皇后は司馬一族に対して曹髦を跡継ぎとすることだけは譲らず、
最終的に曹髦が皇帝となったのでした。
郭皇太后としては、夫であった曹叡と血筋的に近い者を後継者としたかったようで、
これは自分の立場を維持する為の最終ラインでもあったのです。
毌丘倹・文欽の反乱

司馬師・司馬昭の専横に我慢をしていたものの、
曹芳が廃位させられたことに怒りを感じた毌丘倹が文欽と組んで寿春で蜂起します。
漢王朝の未来を案じて立ち上がった毌丘倹・文欽でしたが、
あっさりと司馬師によって鎮圧されてしまうのでした。
そして毌丘倹・文欽の反乱鎮圧で活躍したのが諸葛誕であり、
諸葛亮・諸葛瑾の親戚だと言われています。
司馬師もこの鎮圧に赴いており、
逃げようとする文欽を負っていた際に息子であった文鴦の反撃にあってしまいます。
この際に司馬師は左目が飛び出してしまい、
それが原因となった形で最終的に死んでしまったのでした。
当時の司馬師は、左目の下にできたコブの治療を行った後だったこともあり、
文鴦の突撃の際に傷口が開いたのでしょうね。
司馬師が亡くなった後は、司馬昭が跡を継いでいます。
また毌丘倹・文欽の反乱鎮圧に貢献した諸葛誕でしたが、
その後まもなく自分自身が司馬一族を倒すために反乱を起こしたのでした。
諸葛誕の反乱

毌丘倹・文欽の反乱鎮圧に尽力した諸葛誕が寿春で蜂起します。
諸葛誕の反乱は、
毌丘倹・文欽の反乱とは桁違いの規模であり、
諸葛誕の反乱に呉も援軍を送るなどして協力することとなります。
しかし場内で仲間割れが起こり、
それにつけこまれた形で諸葛誕の反乱は鎮圧されてしまいます。
同じ寿春の地で反乱を起こした毌丘倹・文欽・諸葛誕でしたが、
もう少しきちんと計画を建てて協力して蜂起していれば、
簡単に鎮圧されて終わらなかった可能性も少なからずあった気がしますね。
魏帝曹髦の反乱
郭皇太后の後押しもあって皇帝に即位した曹髦でしたが、
曹操の再来と思わせるほど優れた才能を持った人物でもありました。
しかし曹髦にとって運がなかったのが、
既に曹一族は形上の存在にしかすぎず、司馬一族の世の中になっていたことでした。
曹髦は魏の皇帝でありながら、
この現状を打開すべく司馬昭討伐に乗り出すことになります。
ただ曹髦に味方する者はほとんどおらず、
司馬昭の腹心であった賈充の命によって曹髦は殺害されてしまったのです。
魏皇帝であった曹髦を殺害する事に誰もが躊躇する中で、
賈充は部下に対して「今までお前たちを養っていたのは、この時の為ではないか!!
それに曹髦を殺害したとしても罪に問う事はない!」と叱責し、
これを聞いた部下の成済が曹髦を殺害したという流れでした。
しかし魏皇帝を殺害したという罪は大きく、
「賈充は活かしておくべきではない!」という意見が多い中で、
賈充は部下の成済に全ての罪をなすりつけて、賈充は知らぬ存ぜぬを貫いたのです。
そして曹髦が殺害されたことで、曹奐が即位したのですが、
曹丕に始まった魏王朝は、この曹奐をもって幕を下ろすことになるのでした。

-100x100.jpg)
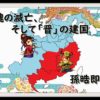
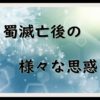
の滅亡-100x100.jpg)

