三国時代の姓諱(姓名)+字に関する秘密
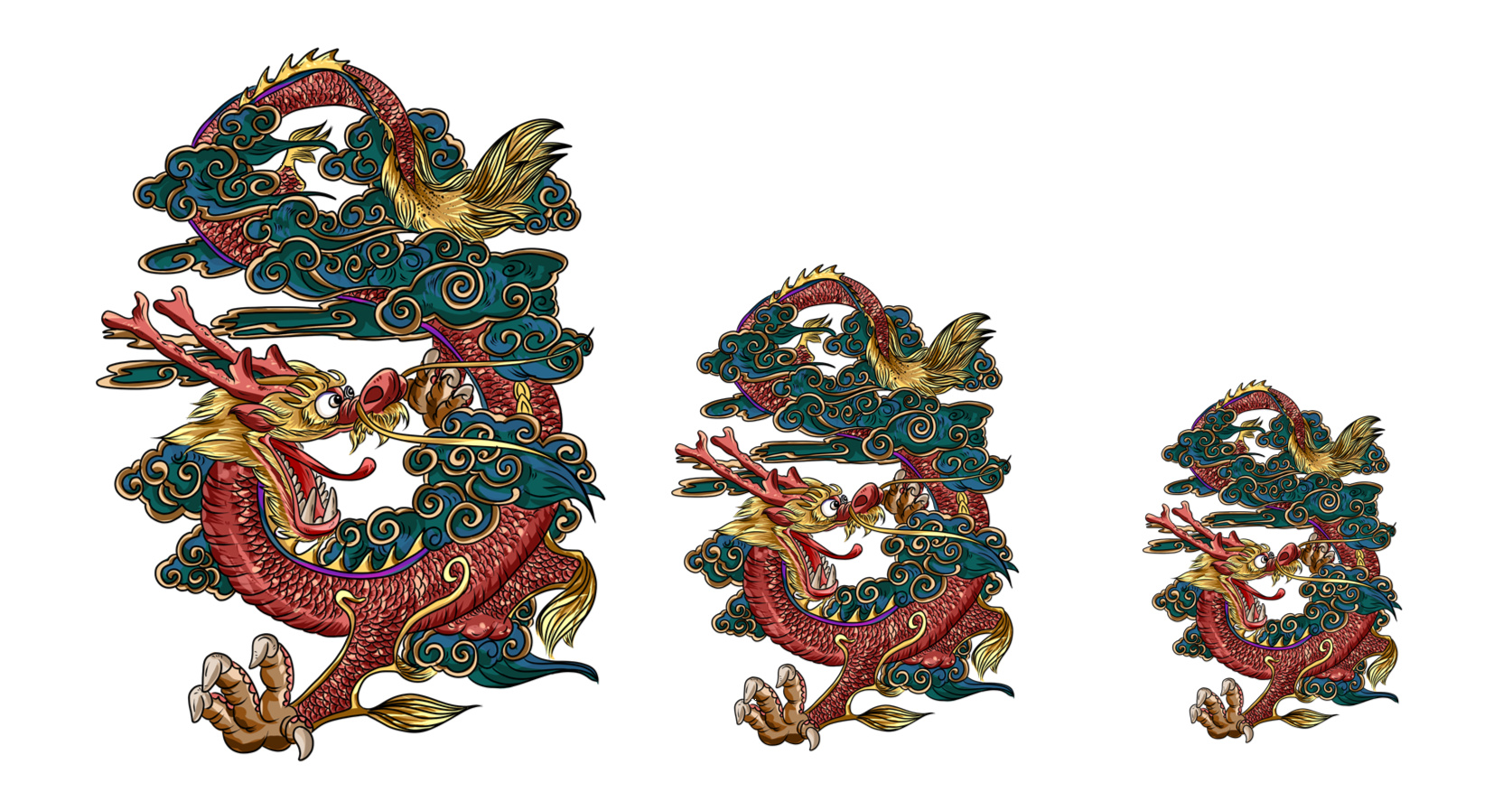
三国志の時代には「姓名(姓&諱)」以外にも「字」というのがありますが、
日本ではだいぶ馴染みの薄いものなので、感覚的によくわからない人もいるかもしれないですね。
日本では「姓名」で馴染み深いので、
例えば織田信長の場合の「姓」は織田で、信長が「名」という感じになります。
もちろんですが、中国にも姓名はあります。
曹操でいうところの、「姓」が曹、「名(諱)」が操ですね。
日本では名前で呼ぶことも多いですが、
三国時代では名前が非常に大事なものとして考えられていたので、
分かりやすく曹操でいえば、「操」とか「そうくん」とか「そうちゃん」なんて呼びません。
ましてや曹操って呼ぶ事なんて更にありえません。
ただ「曹」だけだと、沢山の「曹」って姓の人がいて、誰が誰だか分からなくなってしまいます。
その為の呼び名として、「字」というのがあるのです。
これは本来の名前である、「諱(名)」とは別につける呼称のようなものです。
そうすると曹操は、曹操が「姓諱(姓名)」で、孟徳が「字」ってことになりますね。
ただこの「字」も誰もが呼んでたものではなく、
昔から仲が良かったり、身近な人しか呼んでいなかったのが現状です。
出世して、役職がついてからは、曹丞相や丞相といったように、
「姓+役職名」「役職名」で呼ばれるのが一般的になります。
これは今の日本の総裁や総理大臣に置き換えると分かりやすく、
例えばその時の総理大臣を目の前にして、〇〇さんと基本的に呼ばないのと同じです。
- 安倍晋三→晋三さん
- 菅義偉→義偉さん
- 岸田文雄→文雄さん
- 石破茂→茂さん
- 高市早苗→早苗さん
一般的に「〇〇総理大臣(総裁)」であったり、単純に「総理大臣(総理)」って呼んでると思います。
「山陽公載記」の逸話
山陽公載記には、劉備について次のようなことが書かれてあります。
劉備が成都攻略の際に馬超を仲間にしていますが、
その際に劉備をはじめ周りの多くの者達も馬超を厚遇したわけですが、
ある時に馬超が劉備に対して、劉備と呼び捨てたことがあったといいます。
それを聞いた関羽や張飛は大変怒り、
「あの野郎は生意気だからぶっ殺してやろうか!!」
といった逸話が残されていたりします。
それほどまでに、「諱(名)」を呼ぶことは失礼であると思われていたわけです。
ただ陳寿の「三国志」に注釈を加えた裴松之は、このことについて次のように反論しています。
| 馬超がそんな失礼な事を言うは事は考えられないので、おそらくは作り話であろう。 |
そもそもの話として、劉備の入蜀時に降った馬超と、
荊州の守りを任されていた関羽が出会う接点はなかったはずなので、この点だけを考えても無理があるでしょう。
其一(「諱(名)」と「字」の関連性)
| 「諱(名)」と「字」は、関連づけて付けられることが多いパターン |
劉備玄徳でいえば、「諱(名)」が「備」で、「字」が「玄徳」になりますが、
合わせると「徳を備える」ってなりますよね。
曹操孟徳でいえば「徳を操る」となり、
実際の人柄が偶然にも表れているような漢字にも見えたりします。
他には趙雲(子龍)で使われる「雲」と「龍」は、
必ずといっていいほどにセットで使われる事が多いものになります。
趙雲を例にとったのは、
三国志ファンなら誰でも知っていて分かりやすいからで他にも例があったりします。
例えば陸遜の孫である陸雲(士龍)もまた、ルールに従って名付けられた一人ですね。
其二(部首)
| 「字」と「諱(名)」の部首を揃えるパターン |
虞翻という人物が呉にいますが、「字」を仲翔といいます。
漢字を見ると一目瞭然ですが、「翻」と「翔」を「羽」で揃えてますよね。
其三(伯・仲・叔・季・幼)
| 長男・次男・三男・四男の「字」に、 「伯(他には孟・元・長)・仲・叔・季」をつけていくパターン ※続いて五男(末弟)がいた場合、五男には「幼」が使われる。 |
- 長男→伯・孟(他には元・長など)
- 次男→仲
- 三男→叔
- 四男→季
- 五男→幼
孫堅の息子を例にとると分かりやすいですね。
- 長男:孫策(伯符)
- 次男:孫権(仲謀)
- 三男:孫翊(叔弼)
- 四男:孫匡(季佐)
他にも董君雅の息子達(董卓の兄弟)もそうですね。
- 董擢(孟高)
- 董卓(仲穎)
- 董旻(叔穎)
三男の董旻までしかいないので「叔」で終わっていますが、
もしも董君雅に四男が誕生していたら、「季穎」なんて字になっていたかもしれませんね。
其四(文字の共有)
| 一族の同世代(兄弟など)の文字を共有するパターン |
これがどういうことかというと、「字」の一部に、
「子」「士」「礼」などを共有させるということになります。
この例えの代表例として最も分かりやすいのは、曹操の子供であったりします。
- 曹昂(子修)
- 曹丕(子桓)
- 曹彰(子文)
- 曹植(子建)
- 曹熊(子威)
- 曹峻(子安)
他には「達」で統一され、「司馬八達」の名でも知られた司馬兄弟ですね。
また司馬兄弟の長男から四男までは、「伯・仲・叔・季」の法則も入っていたりします。
- 司馬朗(伯達)
- 司馬懿(仲達)
- 司馬孚(叔達)
- 司馬馗(季達)
- 司馬恂(顕達)
- 司馬進(恵達)
- 司馬通(雅達)
- 司馬敏(幼達)
まとめ
これまで述べてきたように「諱(名)」と「字」には、深い関係性があり、
上で紹介したようにルールがあったりします。
今後こういった事を少しでも意識しながら、
三国志に登場する人物を見ていくと結構面白かったりしますね。
何故なら現在に伝わっていない字を推測できたりすることも可能な場合もあったりするからです。
「馬氏の五常」で知られる馬良・馬謖の三人の兄達もその一例ですね。






