赤壁の戦い(曹操VS孫権・劉備)

官渡の戦いで勝利して間もなく袁紹が病死すると、
袁紹遺児であった袁譚・袁煕・袁尚らの討伐に乗り出して勝利します。
これにより曹操は華北を支配下に置き、
勢いそのままに荊州・揚州を支配下に置くべく進撃を開始したわけです。
真っ先に標的になったのは荊州ですが、
丁度荊州を治めていた劉表がこの世を去ったことで、劉琮が跡を継いだタイミングでした。
当初劉琮は曹操と全面対決する覚悟だったようですが、
周りの者達から諫められ、
結果として戦わずに降伏してしまう事態に・・・
この時に劉備は劉表の世話になっており、
劉琮が降伏したことで、曹操の追撃から逃れる為に南下していくことになり、
曹操は劉備を追って追撃を開始しています。
その後に劉備は孫権と同盟を結んで曹操と戦うわけですが、
これが赤壁の戦いですね。
赤壁の戦いでは劉備・孫権連合軍が、
曹操に勝利をした戦いとして知られていますが、
赤壁の戦いにはまだまだ謎が多く、
赤壁は戦いの中の小さな一部地域だっただけとも言われたりもしますし、
疫病が流行ったことが主な原因で撤退しただけで、
これまで言われているような大きな兵の損失はなかったとも言われたりしていますね。
まぁ実際戦上手であった曹操が、無理な戦いを続投し、
大惨敗を喫したというのも腑に落ちないところはありますから・・・
とにかく赤壁の戦いで曹操が敗れたのは事実で、
次第に曹操・孫権・劉備といった天下を三分する三国志の世界に突入していくわけですから、
三国志を語る上で欠かせない戦いの一つであることは間違いありません。
韓遂・馬超連合軍(関中十部)との闘い

涼州で割拠していた馬騰の息子である馬超が、
韓遂と手を結んで曹操に対して大規模な戦いを挑みます。
三国志演義では騙し討ちにあった父親である馬騰、
弟である馬休・馬鉄などの復讐戦として描かれていますけど、
正史では馬超が反乱を起こしたことがきっかけとなって、
馬騰・馬休・馬鉄といった馬一族が処刑されているのが正確な所ですね。
何が言いたいのかと言うと、
三国志演義では親孝行である馬超の姿が描かれていますが、
正史では親不孝者である真逆の馬超の姿があるわけです。
韓遂も過去何度も涼州・雍州で反乱を繰り返してきた人物であり、
韓遂と馬超が手を組んだことで、曹操は大変な苦戦を強いられることとなったのでした。
最終的に賈詡の離間の計に見事にはまった馬超は、
韓遂と仲違いし、そこを襲われる形で曹操の勝利に終わることに・・・
ちなみに韓遂・馬超連合軍と書きましたけど、
実際は十人の豪族による反乱なわけで、韓遂も馬超もその十人の豪族の一人に過ぎません。
ただ名前的にやはり有名なのは韓遂・馬超の二人でしょうね。
https://daisuki-sangokushi.com/2019/11/24/%e5%8f%8d%e4%b9%b1%e3%81%ab%e7%94%9f%e6%b6%af%e3%82%92%e6%8d%a7%e3%81%92%e3%81%9f%e7%94%b7%e3%80%8c%e9%9f%93%e9%81%82%e3%80%8d/
漢中の戦い(曹操VS劉備)

赤壁の戦いに勝利した劉備は、
曹操領となっていた荊州南部へと侵攻を開始!
そして見事に荊州南部の取得に成功しています。
劉備の勢いはここだけに止まらず更に益州を治める劉璋の領土へと侵攻を開始し、
劉備は苦戦を強いられるものの、最終的に劉璋が降伏したことで終わりを迎えたのでした。
ちなみにですが、劉璋が降伏する少し前に馬超が劉備の元へと馳せ参じています。
ただ劉備が益州を手に入れていた頃に何もしていなかったわけではなく、
曹操は漢中へと侵攻を開始し、
五斗米道の祖でもある張魯を降して、漢中を手に入れていますね。
その後に起きたのが、
漢中の戦い(定軍山の戦い)です。
漢中を守る夏侯淵を黄忠が討ち取った事でも知られる戦いですが、
劉備が初めて曹操に勝利できた戦いでもあるのです。
それまでの劉備は常に曹操に負け続けていてばかりでしたから・・・
https://daisuki-sangokushi.com/2020/05/24/%e5%9c%a7%e5%80%92%e7%9a%84%e6%a9%9f%e5%8b%95%e5%8a%9b%e3%82%92%e6%ad%a6%e5%99%a8%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%b0%86%e8%bb%8d%e3%80%81%e5%a4%8f%e4%be%af%e6%b7%b5/
楊修の「鶏肋」という言葉もこの時に生まれたものです。
三国志演義ではこの言葉をきっかけに曹操に処刑されているんですけど、
史実ではもう少し後で処刑されているので、
この言葉のせいで処刑されたかは結構な疑問が残る点でもあります。
実際は魏諷の乱の闇深さに隠された事実の中で、
処刑されていた可能性もあると個人的には思っていますね。
そのあたりのことは、
以下の記事(魏諷の乱)に記載しているので興味ある方は読まれてみてください。
荊州争奪戦/関羽の失態(曹操・孫権VS劉備)

漢中の戦いで劉備に敗れて漢中を奪われることになった曹操ですが、
漢中での戦い以上に危機的な状況が身近に迫っていました。
荊州の関羽による樊城への侵攻です。
関羽に呼応する者達も多く、長雨が関羽に味方したりで、
樊城は名将曹仁が守っていたものの、
落城寸前まで追い込まれていました。
樊城の援軍に送った于禁はこの長雨のせいで、
戦いもできないまま関羽に投降するという始末で・・・
曹操自身も関羽の侵攻に対して、許昌から遷都を考えるほどだったといいますからね。
しかし孫権が曹操と結んだことで状況は一変します。
孫権が荊州の江陵を襲ったことで関羽は撤退に追い込まれてしまいます。
実際は兵站(食糧輸送)などをきちんと確保できていなかったので、
荊州(江陵)が陥落していなかったとしても、
遅かれ早かれ退却せざるを得なかったかもしれませんが・・・
歴史にもしもが存在していた場合、
孫権の荊州侵攻がなかったならば、
許昌侵攻を許していた可能性も普通にあるので一概には言えない所でもありますけどね。
とにかくこの戦いで劉備は荊州を奪われただけでなく、
劉備・張飛と苦楽を共にしてきた関羽は、捕らえられて処刑されてしまったのでした。
曹操の最後

曹操は魏公・魏王となっており、
残されていたのは皇帝にとって代わるという事だけでした。
臣下の者達も曹操に皇帝になるように進言する者が後を絶ちませんでしたが、
曹操は最後の最後まで皇帝になることなく生涯に幕を下ろします。
このあたりの曹操の心情は、
「述志令」というその時々の心情が記載されたものがあるのですが、
「自分は絶対に皇帝になることはない!」と述べられていますね。
述志令は、その時々(二十歳~五十六歳)の曹操の心情が書かれているものですが、
かなり貴重な資料だと個人的には思ってます。
曹操の遺言は次のようなものだったといいます。
「天下はまだまだ乱れており、葬式を盛大に取り行うことは避けなさい。
それから私の遺体は平服のままで、かつ金銀財宝を一緒に入れる必要もない。
そして葬儀が終わったら服喪はすぐに脱ぎ捨て、
いつも通り仕事を熱心にするように・・・」
そんな曹操らしい言葉を残して220年にこの世を去っていますが、
2009年に曹操の墓が中国河南省安陽で発見されます。
発見された墓は、曹操の墓とも思えない程に質素だったといいます。
まさに曹操の遺言が正しかったと証明する大きな証拠が見つかったわけですね。
曹操がもしこの世に誕生していなければ、
今現在に伝わっていないモノが沢山あったのは間違いありません。
曹操は中華統一することより難しい事を沢山成し遂げた人物であったのです。


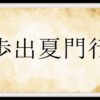

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)


