曹操 -天下の傑物-

曹操が「治世の能臣、乱世の奸雄」と許劭から評価されたことは有名ですが、
それ以外にも曹操は多くの人物から高い評価を受けていました。
曹操は文武に優れた人物であり、多大な功績を後世に残しています。
文学を推奨した事(建安文学)はその代表ですし、
酒の醸造法を後世に資料(九醞春酒法)として残したのも曹操です。
また私達が目にする事もある孫子の兵法書(魏武注孫子)は、
曹操が注釈を加えて読みやすくしたものが今に伝えられています。
日本でも孫子の兵法書は良く読まれた事でも知られていますし、
有名な所で言えば、武田信玄の旗印「風林火山」も孫子の兵法書に書かれた内容の一部抜擢です。
なので信玄が読んだであろう孫子の兵法書も、曹操の魏武注孫子だという事になります。
錦を衣て昼行く(錦を着て昼行く)
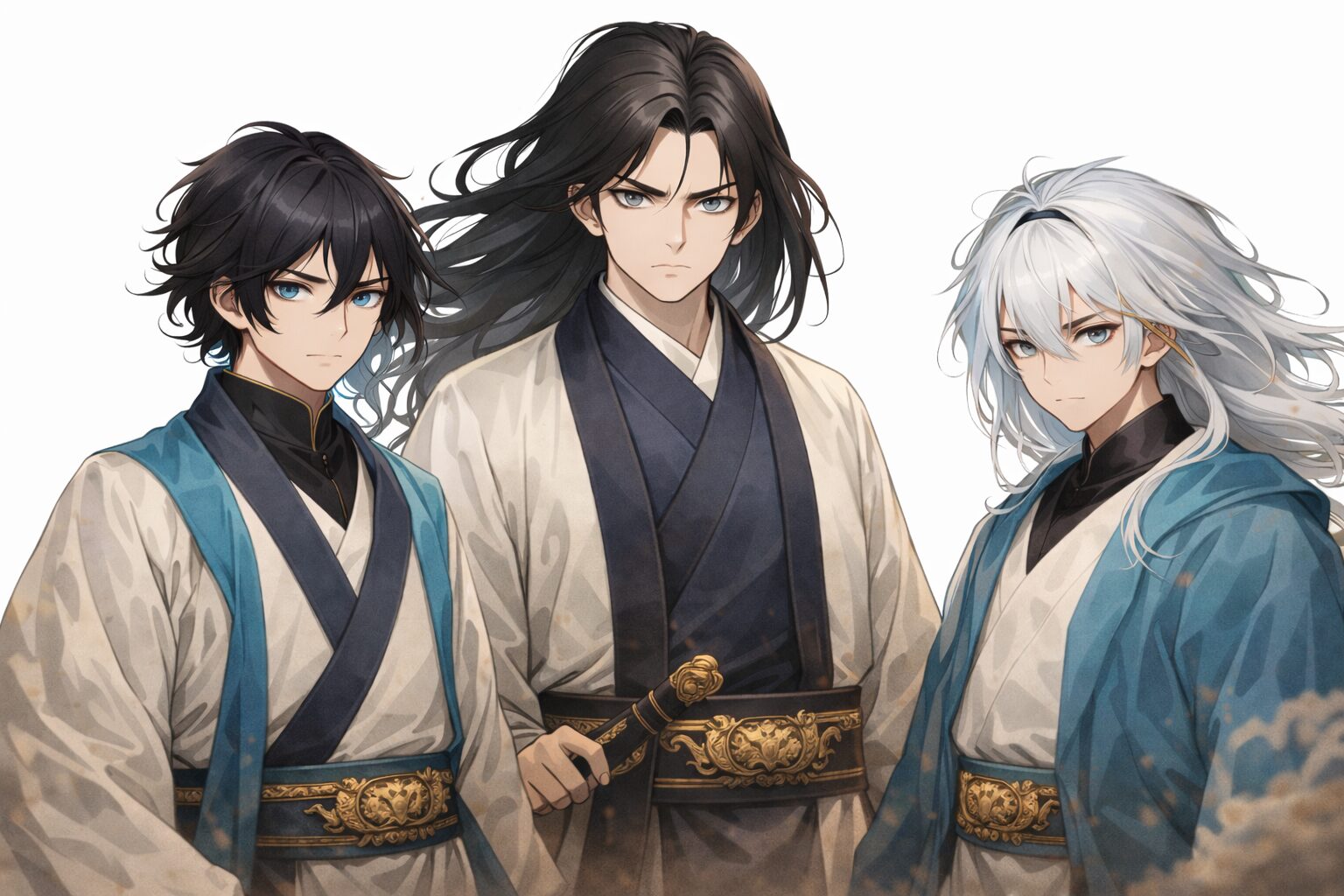
曹操は息子である曹丕・曹植と共に、中国の文学史に多大なる影響を与え、
新しいスタイルの五言詩を確立した事でも知られています。後に建安文学と呼ばれたものですね。
その中でも曹植は頭一つ飛びぬけている程に優れた評価を受けており、
洛神賦は曹植の代表作の一つですし、それ以外にも多くの優れた作品を残しています。
例えば曹丕と曹植の逸話で残る七歩の詩は有名な話だったりします。
ただ七歩の詩は非常に有名ではありますが、正史三国志に記録が残る逸話ではありません。
世説新語に書かれている内容であり、そこから三国志演義に取り入れられた話です。
世説新語と三国志演義の七歩の詩は一部内容は違いますが、大まかな所は同じことを言っています。
| -七歩詩(世説新語の原文&書き下し文&翻訳)-
文帝嘗令東阿王七步中作詩、不成者行大法。 「文帝、嘗て東阿王をして七歩の中に詩を作らしめ、 成らずんば大法を行はんとす。」 曹丕(魏文帝)は曹植(東阿王)に対して、七歩歩くうちに詩を作るように命じた。 そしてもし作れないようならば法に照らして罰しようとした。
應聲便為詩曰、 「声に応じて便ち詩を為りて曰く、」 曹植は曹丕の声に応じて、たちまちのうちに詩を作って読んだのである。
「煮豆持作羹、漉菽以為汁。 「『豆を煮て持って羹を作し、 豉を漉して以て汁と為す。」 「豆を煮て濃い汁物を作り、豆味噌をこして味を調える。
萁在釜下燃、豆在釜中泣。 「萁は釜下に在りて燃え、 豆は釜中に在りて泣く。」 豆萁は釜の下で燃料として燃え、豆は釜の中で泣く。
本自同根生、相煎何太急」 「本同根より生じたるに 相煎る何ぞ太だ急なる。』」 豆も豆萁ももともとは同じ根から生まれたものであるのに (豆がらは豆を煮る為に)どうしてそんなに激しく燃えるのか!?」
帝深有慚色。 「帝、深く慚づる色有り。」 それを聞いた曹丕は深く恥じ入ったのである。 |
| -七歩詩(三国志演義の原文&書き下し文&翻訳)-
煮豆燃豆萁 「豆を煮るに、豆萁を燃やす。」 豆を煮る為に、豆萁を燃やす。
豆在釜中泣 「豆は釜中に在りて泣く。」 豆は釜の中にあって泣く。
本是同根生 「本は是れ、同根に生ずるを、」 豆と豆萁は、もともと同じ根より生じたにも関わらず、
相煎何太急 「相い煮ること、何ぞはなはだ急なる。」 (豆萁は豆を煮る為に)どうしてそんなに激しく燃えるのか!? |
そして今回紹介する「錦を衣て昼行く」は、
曹操らしさが出ている言い回しの一つだと思います。
どういう場面でこの言葉が使われたかというと、それは張既が雍州刺史に任じられた際のことでした。
張既が雍州刺史として任地へ旅立つ際に、
曹操は「衣錦昼行(錦を衣て昼行く)」と言ったわけですが、
これは雍州が張既の生まれた地域の近くだったことで、その言葉を張既にかけたという流れになります。
※ちなみに張既の出身は司隸左馮翊高陵県になります。
今でも耳にすることもあると思いますが、「故郷へ錦を衣て帰る」と同じ意味合いですね。
| 張既殿が雍州へ素晴らしい着物をまとって昼に帰郷するのは、
出世を成し遂げた自分自身の姿を見てもらうための凱旋であるからだぞ。 |
「錦を衣て昼を行く」の語源
曹操が張既に対して用いた「錦を衣て昼行く」ですが、
正確には「魏志」張既伝に「繡を衣て昼行く」と書かれています。
ただ現在では、「繡」ではなく「錦」が使われているというだけになります。
どちらも同じ意味です。
| 太祖謂既曰「還君本州、可謂衣繡昼行矣。」
太祖(曹操)は張既に対して次のように述べた。 「君を本州(故郷)に帰任させるのは、まさに『錦を衣て昼行く(故郷に錦を飾る)』という事である。」 |
そもそもこの言葉は、秦の圧政に怒りを覚えて決起した項羽に由来する言葉になります。
項羽は秦の都である咸陽を陥落させて秦を滅ぼした際に、
配下の者達は、項羽が地元であった楚ではなく、中央に居ることで天下を治めることが可能であると注意を促しました。
項羽はそれに対して「錦を衣て夜行くが如し」と返したわけです。
正確には「史記」項羽本紀に次のように残されています。
| 富貴不歸故鄉、如衣繍夜行、誰知之者
(富貴にして郷に帰らざるは、繍を衣て夜行くが如し。 誰かこれを知る者あらんや。)
出世しても故郷に帰らないのは、立派な服を着て暗い夜道を歩くようなもので、 故郷の人々に知られることなく終わってしまっては意味をなさない。 |
結局配下の者達の言葉を聞かずに、項羽は中央から離れます。
そして自分の故郷であった楚(都:彭城)に戻っていったわけですが、
これがもとで劉邦に付け入る隙を与えてしまい、最終的に劉邦に敗れる事に繋がります。
曹操が張既にかけた言葉は、項羽が使った言葉と基本的に意味は同じですが、
項羽が「故郷に帰らないのは夜に錦を着るようなものだ(=だから自分は帰る)」と自己の願望を語ったのに対し、
曹操は功績を挙げた張既への最大級の賛辞として張既を称えた点で異なります。
華僑と「錦を衣て昼行く」
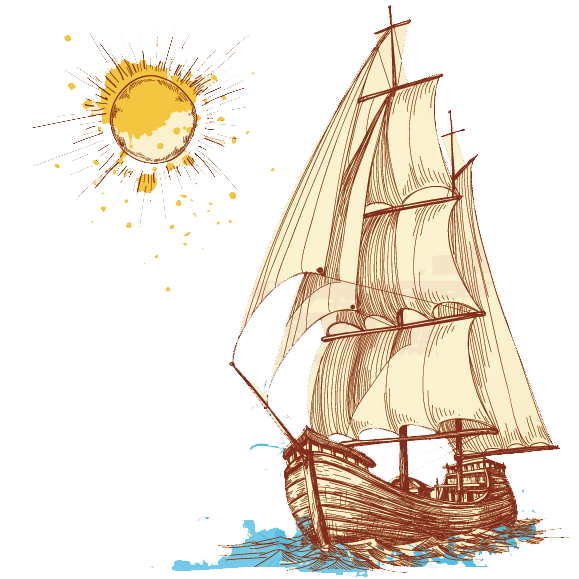
中国には「海水至るところに華僑あり」という言葉があります。
これは中世以降に貿易業の発展によって、
多くの中国人が世界各地に進出して、海外を拠点に根を下ろしたといった意味です。
そんな華僑らが故郷に錦を飾った例が中国各地にみられます。
広州の黄埔古村にある日本楼なんかは、
オランダ風の窓硝子で、レンガ造りのオランダ屋敷(日本の長崎)に非常に似た楼(建物)があったりします。
これは日本に移住した華僑が、一時帰郷した際に、自分の代わりに「楼」を作ったからだそうです。
また日本の長崎に見られたオランダ様式だけでなく、
ローマ様式・アメリカ様式・ギリシャ様式など様々な「楼」が作られていたりもします。

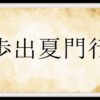

-68b0c46dcad0b-100x100.jpg)


